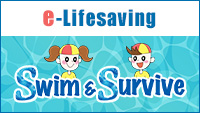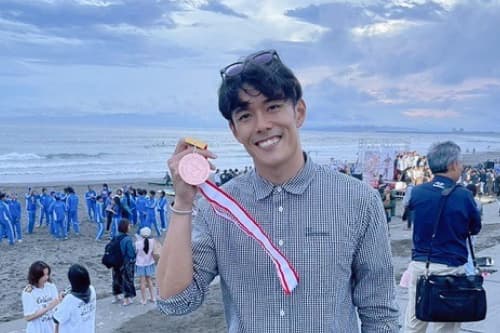ライフセービングを始めたきっかけ
幼少期〜高校まで水泳を長いこと続けてきました。しかし、高校まで水泳をやってきたものの、思い描いていたカタチで終わることができず、不完全燃焼なまま引退してしまいました。中学からの憧れで保健体育の教員になりたいと思い日本大学文理学部体育学科に入学。当初は、特に部活動もサークルにも入る気持ちはありませんでした。たまたまサークル紹介のブースを通りかかったときに、赤と黄色のユニフォームを着た先輩方を見て、「自分はここに入るべきだ。」と思い入部。気づけば今年で16年目になっていました。
ライフセービングとは
この活動の素晴らしい所は、
・人との繋がりを大切にしていること
・自他共に認め、励まし、人として成長できること
です。この活動が成り立っているのは、私達ライフセーバーが凄いからではありません。周りの協力や理解があってこそ、海の事故は減らせるのであり、より多くの人と関わることでライフセーバーは認知され、海水浴客自らが命を守る行動(Watersafety)をしてもらえます。
また、「速く泳げるから一人前のライフセーバーなのか」と言ったらそうでもありません。予測ができない災害に対する意識、レスキュー技術、気象や海(河川)に関する知識など…どれも欠けてはならないし、積み重ねてきた経験や日頃の学びが安心感に繋がり、その強さが「海に笑顔」をもたらすのです。

第二の故郷
九十九里ライフセービングクラブでは大きく8つのエリアに分かれて活動をしています。私は内房エリアの鋸南町を拠点に監視活動を行っています。鋸南町は山と海に囲まれていて、海の家が沢山あって人で溢れた海水浴場ではなく、こじんまりとした海水浴場になっています。幸いにも、私自身が大きな事故に遭遇した事はありませんが、人が少ないからこそ、遊泳区域外での遊泳やSUP、水上バイク、シュノーケルなど様々なマリンスポーツを楽しむ人が鋸南町には多く訪れます。そのため、事故を想定したシミュレーションが欠かせません。地元に愛されている海水浴場でもあり、人が少なく穴場スポットだと訪れる遊泳客や最近では別荘地や新しい宿泊施設の建設によって、客層も変わりつつある鋸南町。
私は、ライフセービングスキルとは別に、自分自身が活動する地域の特色を知り、行政との関係を築くことも大切であると思っています。長く活動をすることで、信頼が生まれ、ライフセーバーの存在を認識してくれます。地元の方の昔話を聞いたり、遊泳客に鋸南町の魅力や海での遊び方を伝えたり。ハードな監視活動の中でもこういった時間を共有できるのもライフセービングの楽しいところです。
かれこれ16年が経ちましたが、私にとって鋸南町は、実家のように帰ってこれる素敵な場所なのです。

恩師との出会い
私がライフセービングを続けてこれた原動力となった人が鋸南チームのディレクターを務めてくださっている江川陽介さんです。江川さんは、西浜・鹿嶋・九十九里の外房エリアでの監視活動を経て、現在鋸南エリアのディレクター22年目となります。日本ライフセービング協会では、アカデミー本部副本部長として資格認定や講習会のカリキュラム調整、指導員養成に携わり、競技安全委員会では競技会運営と安全課の活動を支援しています。さらに大学教員としての顔もあり、多方面からライフセービングに関わり、多くのライフセーバーを育ててくださっています。恐らく、江川さんと出会っていなければ、ここまでライフセービングに向き合っていなかったでしょう。江川さんの教えは1つ1つ重みがあり、自分の個性を最大限に引き出してくれました。私が1年目で江川さんから伝えられたこととして、今でも覚えているのが、「無事故で一夏終えたのは、ただ単に確率の問題であって、気づかない所で人は亡くなっている。1年を通して事故がなくなることが我々の目標である。」「ライフセーバーとしての誇りを持ってほしい。」
ということです。
私は、活動を続けていくことで、ライフセーバーに求められるものは、単なる「守り人」だけでなく、「寄り添える人」なんだと気づくことができました。

大学卒業後のライフセービング
大学卒業後は、中学・高校の保健体育の教育免許を取得し、非常勤講師として勤務しました。社会人になってもライフセービングは続けたいと思ったのと、自分自身のステップアップにとインストラクターの資格を取得。夏は学生と共に監視活動に励みました。競技の方も力を入れておりましたが、台風や新型コロナウイルスの影響もあって大会は中止。学生の頃のように時間を費やせなかったのもあり、これを機に競技からは離れてしまいました。(また復活できたら…)
現在は、仕事も退職をしており、1児の母として子育て中です。しかし、チームから離れることはなく、定期的にチームメンバーとやり取りしたり、可能な限り夏の監視活動に携わったりと「今できること」を全力でやっております。
未来のライフセーバーに繋げる為にも、大学を卒業した社会人がどう継承していくかが課題であり、時代や環境の変化に対応した自分自身のアップデートも必要であると感じています。

最後に
実はこのコラムのバトンを繋げてくれたのは、同期の三井結里花さん。彼女のような素晴らしいオーシャンウーマンではないし、特別実績があるわけではないけれど、私なりのライフセービングを。そして、強くて、優しくて、かっこいいママライフセーバーを目指したいと思います!
・日本大学サーフライフセービングクラブ ZIPANG 卒業
・九十九里ライフセービングクラブ所属
・サーフライフセービングアシスタント指導員
・遊び盛り3歳の娘の育児に奮闘中